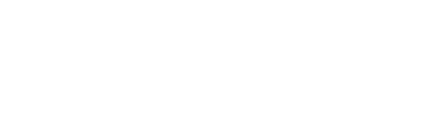広島市立学校が授業再開 今年度の対応策と見通しについて 広島市議会議員・むくぎ太一(椋木太一)
こんにちは、広島市議会議員(安佐南区、自由民主党)・むくぎ太一(椋木太一)です。
新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、広島市立学校(幼稚園、小・中・高校、中等教育学校、特別支援学校)は臨時休校の措置を取っていましたが、6月1日から通常の学級編制による学校教育活動を再開しました。未曽有の国難とも言うべき事態で、ここまで耐え忍んできた子どもたちや保護者の皆様、そして、教育関係者の方々のご苦労・ご努力に敬意を表したいと思います。
今回の学校再開に対しては、新型コロナウイルスの「第2波」「第3波」の可能性や危険性も指摘されていることなどから、慎重な対応を求めるご意見もいただいております。また、政府はこのほど、「9月入学」の来年度の導入を見送りました。私は、新型コロナウイルスと向き合いながら前進していかなくてはならないと思っておりますし、かねてより、「9月入学」の議論をこのタイミングで行うべきではないと申し上げておりました。そうした思いのもと、広島市の考え方を踏まえ、皆様からいただいた、学校再開や「9月入学」に関するご質問やご意見に、Q&A方式でお答えしたいと思います。
Q1 今年度中にカリキュラムを消化できるのでしょうか?
A 5月31日現在、広島市立の小・中学校では、臨時休校によって29日の授業日数が不足しています。夏休みと冬休みを短縮することで計21日(夏休み17日、冬休み4日)の授業日数を確保します。残り8日分は、運動会や卒業式の練習時間を削減したり、野外活動や学習発表の日数を減らしたりすることよって確保するよう、各学校で授業や行事を精査しているところです。
Q2 「詰め込み」になるのではないか?
A Q1のとおり、授業の精査を行っているところですが、広島市立学校では1日7時限以上の授業を行うことを想定していません。1日6時限で年度内にカリキュラムを消化するため、朝学習(15分間)を3日行うことで授業1コマ(45分)を確保するような、柔軟な運用も含めてカリキュラムの再編成にあたっています。
Q3 8月の暑い時期に授業を受けるのは子どもたちへの虐待につながるのでは?
A 広島市立学校のエアコン普及率は、音楽教室や理科室といった特別教室を除くと、ほぼ100%となっています。「密」の状態を避けるため換気をする必要があるため窓を開けることにはなります。ただ、換気の頻度は、国の指針によると「30分に1度」が望ましいということですので、授業中、窓を開けっ放しにする状態は考えにくいことになります。
Q4 学校行事をやめると子どもたちの楽しみや思い出を奪う
A このご質問に関しては、私の考えを述べさせていただきます。確かに、野外学習を本来は2泊3日のところを1泊2日に短縮したり、一部の行事を中止にしたりせざるをえないケースは出てくるでしょう。しかし、Q2でも触れましたが、広島市立学校では、「すべての行事を中止にして、朝から晩まで授業漬けさせる」といった状態は想定していません。さらに、冒頭に申しましたように、新型コロナウイルスの感染拡大は「国難」とも言うべき事態です。いわば、災害が発生した状態と考えるのが自然です。平時の環境に限りなく近づけていくことが、私たちに今、求められていることであり、同時に、有事だということを子どもたちに理解させ、その中で対応させていくことも必要なのだと思います。決して、子どもたちをないがしろにしようとしているわけではないことをご理解いただけたらと思います。
Q5 「第2波」「第3波」が来たらどうするのか?学校再開は時期尚早ではないか?
A 学校再開に慎重になられる方々の多くが投げかけられるご質問です。新型コロナウイルスに限らず、未来永劫、平穏無事ということはまずありえません。何かしらの形で、「良からぬこと」は起きます。新型コロナウイルスの「第2波」「第3波」を含め、「良からぬこと」が起きたときに、ダメージを最小限に抑え、一刻も早く対応できるように準備しておくことが重要だと思っております。確かに、新型コロナウイルスの「第2波」「第3波」の可能性を否定できません。しかし、私たちには「第1波」で得た経験・知識があります。基本的なことになりますが、感染拡大を最小限に抑える経験を活かしていくほかはないのです。幾多の困難を前に進んできた、それが人類の歴史だからです。
Q6 「9月入学」の話は何のためにしていたのですか?
A 臨時休校による学習の遅れを取り戻そうと、当初は今年度の9月を新学期にするという想定で議論が始まったようです。しかし、いつの間にか、来年度以降の導入に話が変わっていました。また、「グローバル化」を主張する政治家や評論家が出てきたこともあり、論点が分かりづらくなってしまったように思います。
私は「9月入学」に関して、賛成でも反対でもありません。ただ、国難とも言うべきこの状態で、社会構造を大きく変えてしまう「9月入学」の議論を持ち出すべきではないと思っています。学校現場は目の前の懸案に対応するため、大変な労力を割かれています。「9月入学」という制度変更が重なれば、間違いなく現場はパンクします。経済的にも家計は大きな打撃を受けています。そのような議論を悠長にしている余裕はないのです。そもそも、「9月入学」は、学校分野だけの話にとどまりません。会計年度の変更、企業の採用活動、国家試験の期日見直し、未就学児の問題、保育園の待機児童問題(福祉分野に当たります)など、枚挙にいとまがありません。とはいえ、受験を控えた高校3年や中学3年の不安は、そのほかの学年よりも大きいと思います。ただ、上述のようにカリキュラムを柔軟に運用することで対処できると思います。そうした目の前のことに注力することが、子どもたちのためになるのです。

「9月入学」見送りを報じた新聞と広島市の資料